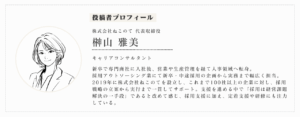採用ターゲットの設定方法とペルソナ活用術|ポイントは「組織の課題解決」目線!
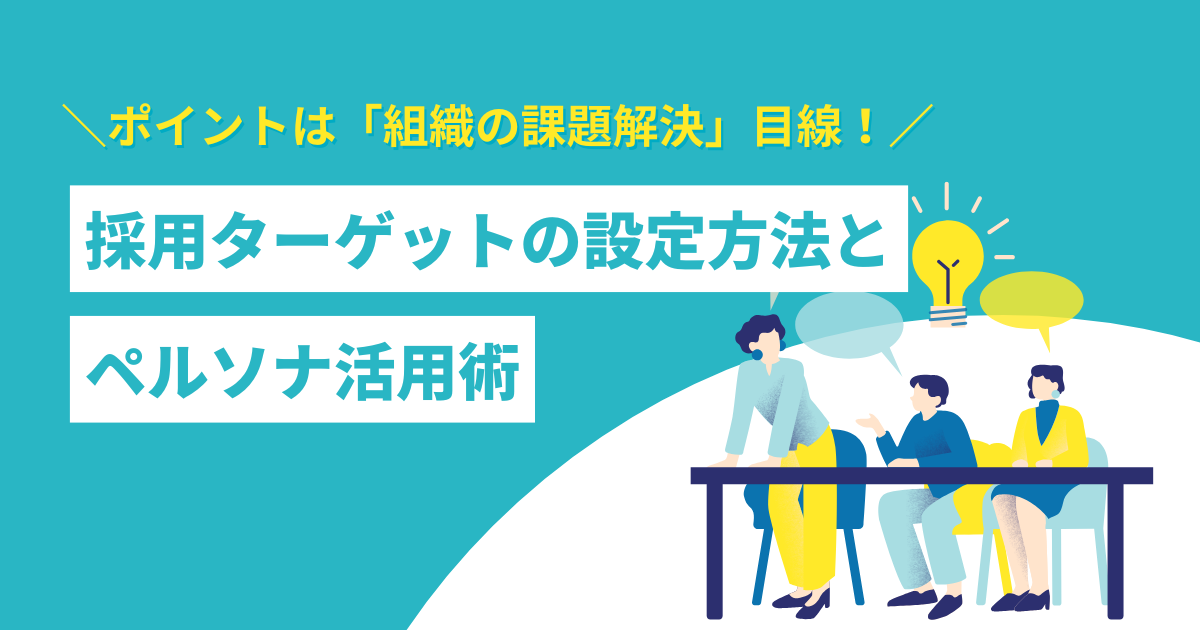
公開日:
「どんな人に自社で活躍してほしいか?」 この問いに即答できますか?もし答えがぼんやりしているなら、採用ターゲットの見直しが必要です。採用ターゲットをしっかり定めることで、自社が本当に求める人材に響くアプローチが可能となり、採用ミスマッチの防止にもつながります。
本記事では、採用ターゲットの定義やペルソナとの違い、設定方法から活用ポイントまでプロの視点で解説します。貴社の採用力向上にぜひお役立てください。
採用ターゲットとは何か
採用活動の第一歩は、「どんな人を採用したいのか」を明確にすることです。
ここでは、採用ターゲットの基本的な定義と、採用ペルソナとの違いを分かりやすく解説します!
採用ターゲットの定義
採用ターゲットとは、自社が求める人材要件を満たす層のことを指します。ここでいう人材要件とは、求める人材のスキル・経験・性格・価値観などを具体的に言語化したものであり、それら条件に合致する候補者の層全体が「採用ターゲット」となります。このターゲットを明確にすることでどのような人材にアプローチすべきかがはっきりします。逆にターゲットを曖昧にしてしまうと、企業と応募者の間でミスマッチが起きやすくなり、結果として早期離職などのリスクを招きかねません。そのため、採用活動を始める第一歩として、まず採用ターゲットを定めることが重要です。
採用ターゲットと採用ペルソナの違い
採用ペルソナとは、採用ターゲットに基づいて設定される具体的な「理想の人物像」のことです。採用ターゲットが年齢や経験などで括られた「層」であるのに対し、ペルソナはまるで実在する一人の候補者であるかのように詳細に描かれた人物像を指します。
例えば、採用ターゲットが「20代・法人営業経験者・向上心旺盛」といった属性であれば、採用ペルソナでは「28歳男性、法人営業6年目。顧客志向が強く、自己研鑽に励む」など、具体的なストーリーを持った人物像を作り込みます。ペルソナを設定することで、ターゲット像だけでは掴みにくい候補者のニーズや価値観まで想定しやすくなり、アプローチ方法や求人票に盛り込む訴求メッセージをより練りやすくなります。
つまり、ターゲット=狙う母集団、ペルソナ=母集団を代表する架空の個人像と考えると分かりやすいでしょう。なお、ペルソナは1つに限定される必要はなく、ポジションや採用目的に応じて複数のペルソナを設計することも有効です。
採用ターゲットを設定するメリット
採用ターゲットを明確にすることによって、採用活動には次のようなメリットがもたらされます。
採用活動の効率化と的確なアプローチ
ターゲットが定まると、自社の魅力や働くメリットをそのターゲットに合わせて訴求しやすくなります。求職者が仕事選びで重視するポイントやニーズを踏まえてアプローチ方法を検討できるため、無駄打ちの少ない効果的な採用広報が可能になります。さらに、ターゲット層が良く利用している求人媒体やプラットフォームが把握できれば、そこに注力して母集団を形成できるため採用活動の効率が飛躍的に向上します。結果として、少ないコストで質の高い応募者を集められる可能性が高まるでしょう。
選考基準の統一による公平な採用
採用ターゲットを明確化することは、選考プロセスの質の向上にもつながります。採用活動は人事担当者だけでなく現場面接官など複数名で進めるものですが、ターゲットが共有されていれば「自社が求める人材像」について関係者間で認識のズレがなくなります。面接官ごとの評価基準のバラつきが減り、選考のブレを防げるため、面接の質を一定水準に保つことができます。その結果、属人的な判断に頼らない公正な採用が実現しやすくなり、採用に関わる意思決定もスムーズになるでしょう。
ミスマッチの防止と定着率向上
「採用がゴール」ではなく、「採用した人材が定着・活躍すること」が本来の目的です。しかしターゲット設定が甘いと、入社後に「こんなはずではなかった」とミスマッチが生じ、早期離職につながるケースも少なくありません。採用ターゲットを適切に設定しておけば、求人票や面接で求める人材像を具体的に提示できるため、求職者側も応募段階で自分との適合度を判断しやすくなります。これにより、入社後のミスマッチが減り、社員の定着率や活躍度合いが向上するため、企業と候補者双方にとって納得感の高い採用プロセスにつながるのです。
すぐに実践できる!採用ターゲットの設定方法
ここからは、採用ターゲットを具体的に設定するための基本的なステップについて解説します!
人材要件を明確にする
採用ターゲット設定の第一歩は、どんな人材を必要としているのかを洗い出すことです。この段階では、募集ポジションや自社の状況を踏まえ、理想の人材に求める条件をできるだけ具体的にリストアップします。
採用ニーズの洗い出し
まずは、現場や経営陣と採用の背景や目的を整理することから始めましょう。特に重要なのは、「この採用で何を解決したいのか」という課題を明確にすることです。採用活動は単なる人員補充ではなく、企業が抱える課題や目標を解決・達成するための手段です。
例えば、「営業力を強化したい」「マネジメント層を厚くしたい」「新規事業を立ち上げたい」など、採用を通じて実現したいゴールを言語化しましょう。そうすることで、「どのような人材に何を任せたいのか」「その人に求める役割やスキルは何か」が明確になり、ターゲット設計の精度が高まります。
MUST条件・WANT条件の優先度設定
人材要件を列挙したら、次にそれらを「MUST条件」と「WANT条件」に仕分けします。【MUST条件】とは絶対に譲れない必須条件、【WANT条件】とはできれば満たしていてほしい歓迎条件です。この優先順位付けによって、ターゲット像のコアとなる条件と柔軟に調整できる条件が整理されます。
なお、具体的な優先度のつけ方や検索条件の絞り込みに関するノウハウについては、以下の記事でも詳しく紹介しています!
採用ペルソナを設計する
続いて、洗い出した人材要件をもとに採用ペルソナを作成します。ペルソナ設計では、先ほど定義したターゲット層に属する架空の人物を想定し、可能な限り詳細なプロフィールを描きます。氏名・年齢・性別から、現職の業種職種、役職、スキルセット、働く目的、価値観、ライフスタイル(趣味や休日の過ごし方、家族構成)など、その人物のバックグラウンドや人となりを具体的に設定してみましょう。ポイントは、「その人物が実在しているかのようにリアルに思い描く」ことです。ペルソナを描く過程で「この人は何を重視して転職活動をするだろうか?」「どんな言葉に心が動くだろうか?」と考えることで、後の求人内容に盛り込む訴求ポイントが見えてきます。
社内の成功事例を参考にする
自社で活躍している人材の共通点を探ることも、採用ターゲット設定の精度を高める有効な方法です。すでに社内で活躍している社員たちは、自社にフィットする人物像の具体例ともいえるため、スキルや価値観、志向性などを分析することで「どのような人材をターゲットにすべきか」のヒントが得られます。
さらに、そうした情報をもとにペルソナを描いていくと、より実践的な採用設計が可能になります。例えば、「トップセールス社員は皆○○の経験がある」「定着率の高い社員は△△な価値観を持っている」など、見えてきた傾向をペルソナの設計に反映させましょう。
また、現場社員へのヒアリングも有効です。「どんな人がチームに加わると戦力になるか」「逆にどんなタイプだとうまくいかないか」といった生の声は、採用担当者だけでは気づきにくい視点をもたらしてくれます。こうした情報をもとに、ターゲット像に具体性を持たせていくことで、実態に即した説得力のある採用ターゲットの設計が可能になります。
データを活用して精度を高める
客観的なデータ分析も取り入れて、採用ターゲットの精度をさらに高めましょう。例えば、社内で活躍している社員に共通する資質を統計的に洗い出す手段として適性検査の活用が考えられます。適性検査によって社員の性格傾向や思考パターン、価値観などを測定し、活躍人材の傾向を数値で把握します。その結果を人材要件の検討材料にすれば、「〇〇な傾向を持つ人は社内で活躍しやすい」という裏付けのあるターゲット設定ができるでしょう。
また、市場のデータも見逃せません。例えば有効求人倍率や応募者数の推移など採用市場の統計データを調べ、ターゲット層の人材がどの程度存在するのか、競合他社の採用状況はどうか、といった情報を集めます。それにより、設定したターゲット像で現実的に採用可能か、必要に応じて条件緩和が必要かといった判断材料が得られます。主観と客観双方のデータを用いて仮説検証しながら、ターゲット設定をブラッシュアップすると良いでしょう。
採用ターゲット設定時のポイントと注意点
採用ターゲットを設定する際には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。自社の状況を踏まえ、以下の観点でターゲット像を見直すことで、より実効性の高い採用戦略につなげることができます。
自社のビジョン・ミッションを再確認する
採用ターゲットを考える際には、まず自社のビジョンやミッションを改めて整理し直すことが重要です。社員が共感し、方向性を共有できるビジョンやミッションは、エンゲージメントの向上にもつながる大切な要素です。
そのため、採用活動においても、企業として目指す姿や大切にしている価値観を土台とし、それらに合致する人物像を洗い出すことが、ターゲット設定の第一歩になります。単にスキルや経験だけでなく、「自社の想いに共感してくれるかどうか」という視点も含めて、ターゲット像を描いていくことが求められます。
目先の人手不足解消だけを考えてターゲットを設定すると、長期的には自社の方向性と合わず戦力化しない恐れがあります。採用ターゲットは企業戦略の一環と捉え、経営層ともすり合わせて決定すると良いでしょう。
解決したい課題から逆算してターゲットを考える
採用ターゲットを設定する際は、どんな人を採用するかだけでなく、採用によって解決すべき課題や、達成したい目的を明確にし、そこから逆算して考えることが重要です。採用は人員を増やすことが目的ではなく、企業が抱える課題や達成したい目標を実現するための手段です。「営業組織の売上を伸ばしたい」「新規事業を任せられる人がいない」といった課題がある場合、それを解決できるスキルや経験を持つ人が、自然と採用ターゲットになります。「この人の採用によって、どの課題が解決できるのか?」という問いを明確にすることが、ブレないターゲット設計のカギです。
採用市場の動向を把握する
採用ターゲット設定は社内要因だけでなく、社外の人材市場の状況も考慮する必要があります。業界全体で人材不足が深刻な職種を無理に採ろうとしていないか、市場価値の高いスキルを求めすぎていないか、といった視点でターゲット像をチェックしましょう。
例えば、ITエンジニアなど競争が激しい人材を狙う場合、そのままでは母集団形成が難しいかもしれません。対策としてターゲット像のハードルを下げる(必須条件を緩和する)、あるいは他社にはない独自の魅力を打ち出すことでターゲット層に振り向いてもらう工夫が必要になります。また、最新の採用トレンドや有効求人倍率などを定期的に把握し、状況に応じてターゲット設定を見直す柔軟性も持ちましょう。
採用ターゲットの設定から実際の採用活動まで、『ねこのて』がサポートします!
採用ターゲットを設定しても、「実際にどうすればいいか分からない」「ターゲットを定めても応募が集まらない」などの課題を感じていませんか?
株式会社ねこのては、採用ターゲットやペルソナの設定から、ターゲットに響くスカウトメールの作成、最適な求人媒体の選定・運用まで、採用活動のあらゆる業務を専門スタッフが代行いたします。
「ターゲットに届く採用広報をしたい」「採用活動をもっと効率化したい」など、採用に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
採用ターゲットの設定は、企業が求める人材像を鮮明に描く作業です。これを行うことで、採用チーム全員が同じゴールに向けて動けるようになり、選考基準の統一や採用ミスマッチ防止にも効果を発揮します。さらにターゲットを軸に据えることで、求人内容やアプローチ方法に一貫性が生まれ、応募者にも企業の魅力が伝わりやすくなります。常にターゲットを意識した採用活動を心がけ、必要に応じて軌道修正しながら、自社に最適な人材を効率よく獲得できる採用戦略を築いていきましょう。