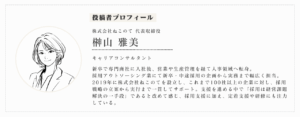採用とは?つい見落としがちな“本来の目的”と成功に紐づく基本3ステップ
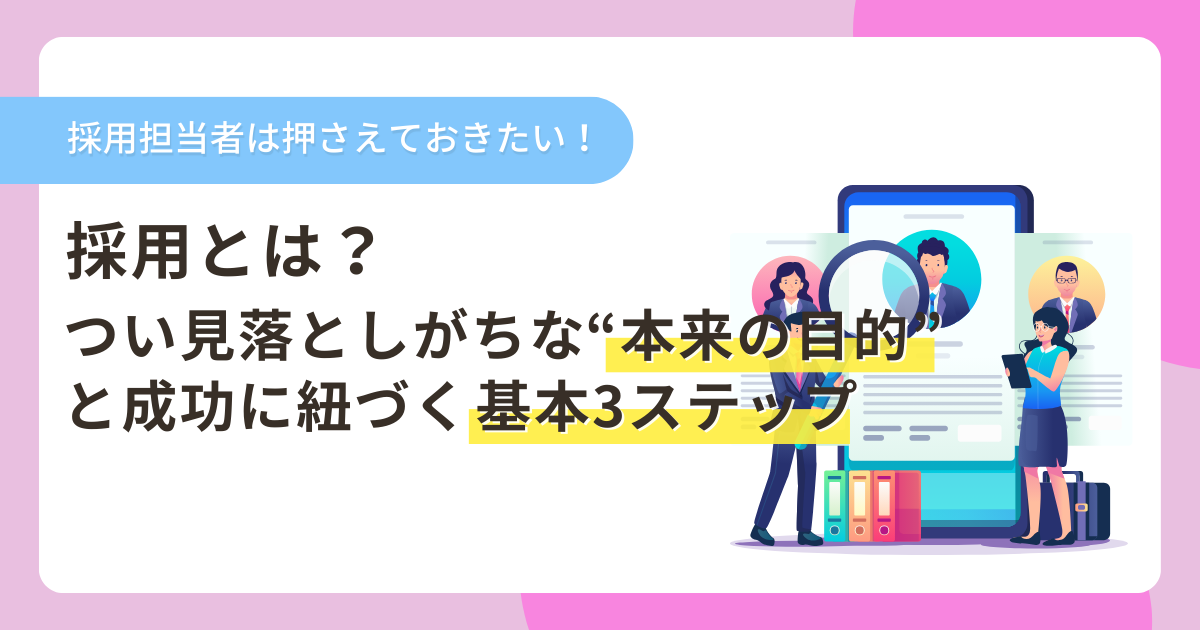
公開日:
企業の採用担当者にとって「採用とは何か」を正しく理解することは、人材確保だけでなく企業の課題解決につなげる上で非常に重要です。
本記事では採用を単なる人材補充ではなく戦略的に捉えるプロの視点から、「採用とは何か」を解説。採用の基本的な意味や目的から、採用活動の種類、さらに企業課題に連動させた採用戦略の立て方や成功のポイントまでを網羅した有益なガイドとなるはずです。
採用とは何か?
人事領域における「採用」とは、企業が必要とする人材を選び出し、組織に迎え入れる一連の活動のことです。単に人手不足を埋めるだけではなく、自社が抱える課題や目標を達成するために適切な人物を戦略的に選定・獲得する行為が本質です。採用は企業の重要な柱である「ヒト」を通じて、企業の成長と課題解決を支える役割を担っています。
採用の目的
企業にはそれぞれ掲げるビジョンやミッションがあり、その実現に向けた経営戦略や事業計画が策定されています。日々の企業活動は、そうした計画に基づいて進められますが、その過程では必ずと言っていいほど乗り越えるべき課題に直面します。
こうした課題に対して企業は、社員のスキルアップや業務の効率化、外部リソースの活用など、さまざまな手段を検討し、そのなかの一つとして「採用」という選択肢が存在します。
採用の本質は「自社の課題解決」にある
採用の本質的な目的は、「自社の課題を解決すること」にあります。採用は単なる人手の補充ではなく、自社が抱える課題を乗り越えるための手段の一つに過ぎません。自社が今どんな壁に直面しているのか、今後どのような変化に備える必要があるのか——そうした課題を明確にしたうえで戦略的に行う必要があります。
こうした課題の一例として、事業内容の変化に伴い社内にないスキルや新しい発想が求められることがあります。その解決策として、既存社員を育成することも考えられるが時間がかかるため、必要なスキルや経験を持った人材を外部から迎え入れることが、最も効果的な解決策となることもあります。
このように採用は、自社の状況や課題に応じて多様な目的で行われます。
以下で代表的な2つのケースをご紹介します。
人員不足・欠員の補充
定年や退職・異動による欠員が生じた場合、そのままでは業務遂行に支障が出ます。社員への負荷増大や生産性低下を防ぐため、不足する人手を補うことは採用の基本目的の一つです。
しかし、欠員が出たからといってすぐに新たな人材の採用に踏み切るのではなく、一度そのポジションの業務内容や体制を見直すことが重要です。まず、退職した社員が担っていた役割や日々の業務を洗い出し、その上で新規に人員を補充しなくても、既存社員の配置転換やスキルアップによって欠員をカバーできないか検討します。例えば、担当業務を他のメンバーに分担したり、教育によってスキル習得をすることで対応できる可能性もあるでしょう。また、業務プロセス自体を見直して無駄を削減したり、デジタル技術を活用して一部業務を自動化することで、人手不足を解消できないかも検討すべきです。
それでもなお人員補充が必要だと判断した場合に、初めて新規採用に踏み切るのが適切なプロセスと言えます。適切なプロセスを経て「やはり人員補充が不可欠だ」という結論に至った場合は、人手不足が慢性化すれば既存社員の離職リスクも高まる可能性があるため、早めの人員確保で業務の安定化を図りましょう。
組織拡大・将来への人材投資
新規事業の立ち上げや支店展開などで組織を拡大する際、リーダーや専門人材の補強が必要になります。また5年先、10年先を見据えた幹部候補の確保・育成も重要になるでしょう。このように事業成長や将来ビジョンの実現に向け、あらかじめ人材を採用しておくことも目的となります。組織の持続的成長のため、計画的な人材投資としての採用が行われています。
採用の種類
採用が自社の課題解決に最適だと判断したら、次に検討すべきはどのような人材を、どのような形で迎えるかです。採用活動は、その対象となる人材によって新卒採用、中途採用、第二新卒採用などに分かれます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的に合った採用形態を選ぶことが重要です。
ここでは、主な採用の種類とその特徴を具体的に見ていきましょう。
新卒採用
新卒採用とは、高校や大学を卒業予定の学生を対象に、企業が毎年定期的に実施する採用活動の一つです。
日本では一般的に、学生が卒業後の4月に一括して入社する仕組みが採用されています。そのため企業側は、採用計画を立ててスケジュールに沿った広報活動や説明会、選考プロセスを行います。
企業が新卒採用を行う主な目的は、自社の将来的な発展を支える人材を安定的に確保することにあります。新卒者を採用するには教育や研修などのコストや時間がかかりますが、長期的な視点で自社の人材を育てたいと考える企業にとって、多く採用されている方法です。
第二新卒採用
第二新卒採用とは、新卒入社後比較的短期間(おおむね1~3年以内)で離職し転職活動を行う若手人材を採用する形態です。第二新卒は、基本的なビジネスマナーを身につけていることが多く、一から教育する必要が少ないため、育成コストや時間を抑えやすい点が特徴です。一方で、実務経験が十分ではないケースもあるため、企業側は将来性を重視した採用と、入社後のフォロー体制に配慮することが求められます。
新卒採用が計画通りに進まず若手人材が不足している場合や、将来性のある人材を通年で確保したい企業にとって、有効な採用手段の一つです。
中途採用
中途採用とは、他社での就業経験がある人材を企業が採用する方法のことを指します。業務上すぐに貢献できる即戦力を求めて採用するケースが多く、特に欠員の補充や新たなプロジェクトの推進など、迅速な対応が必要な場面で効果を発揮します。特に前職が自社と同業界であれば、業界特有の知識や専門スキルを即座に活かすことができ、入社直後から業務への貢献を期待できるでしょう。
中途採用の大きなメリットは、他の企業で得られたさまざまな経験やノウハウを社内にもたらしてくれる点にあります。これまで社内にはなかった新たな視点やアプローチによって、企業が抱える課題解決や業務改善が促進されます。
その他の採用形態
採用活動には、上記以外にも多様な形態があります。契約社員やアルバイトは、業務量や期間に応じて柔軟に人材を確保でき、繁忙期や限定的なプロジェクトにも対応可能です。派遣社員は即戦力を短期間で確保できる手段として有効で、採用や労務管理の負担も軽減できます。また、副業・兼業人材の活用は、高度な専門スキルを部分的に取り入れたい場面に適しており、コストを抑えながら外部知見を得る方法として注目されています。各形態の特性を理解し、状況に応じて活用することで人材戦略の幅を広げられるでしょう。
▼関連記事:採用の種類によって、採用チャネルも使い分けることが大切です。代表的な採用手法の比較については、以下で詳しく解説しています!
【2025年版】多様化する採用手法の種類と特徴を比較|最適な手法を選ぶコツとは?
採用計画の立て方3ステップ
採用活動を成功させるには、場当たり的に人を集めるのではなく企業の課題と連動した戦略的人材採用が重要です。厚生労働省の「人材活用ガイドライン」では、経営者と人事担当者が協働し課題の本質を見極めた上で人材戦略を検討することを推奨しています。
ここでは経営目線で採用計画を立てるための3つのステップを紹介します!
ステップ1:企業課題と人材ニーズの明確化
まず自社の経営方針・事業計画を踏まえ、現在の課題を洗い出します。「市場拡大に対応するには?」「生産性向上にはどんな方法があるか?」といった観点から、課題の本質や要因を明確にすることが出発点です。その上で、人材確保や業務の見直し、既存社員のスキルアップ、ITツールの導入など、課題の解決に必要な手段を幅広く検討しましょう。仮にその中で「人材を新たに確保する必要がある」と判断した場合は、どのようなスキル・経験・役割を持つ人材が必要かを明確にし、具体的な要件を定義していきます。ここで経営層の意図(ミッション・ビジョン・バリュー)も踏まえ、人材像を具体化することがポイントです。
ステップ2:採用戦略・計画の策定
明確になった人材ニーズに基づき、いつまでにどのような人材を、どの手段で採用するかという採用戦略を立てます。新卒・中途や正社員以外の活用(派遣や業務委託)も検討し、最適な採用チャネルを選択します。
また、採用プロセス上で評価すべきポイント(採用基準)も策定しましょう。仕事で成果を出している社員に共通する行動や考え方や企業文化との適合性など、評価軸を決めておくことで、面接官ごとの判断ブレを防ぎ経営方針に沿った人材を見極めやすくなります。
ステップ3:採用プロセスの実行と改善
戦略に沿って実際の採用活動を展開します。求人票や募集内容には経営層のメッセージやビジョンを反映させ、求職者に自社のミッションや魅力が伝わるよう情報発信しましょう。
選考過程ではスピード感を持ちつつ丁寧なコミュニケーションを図り、内定後もフォローを行って入社意欲を高めます。採用活動の結果については、定着率や活躍度合いを追跡し、計画とのギャップがあれば原因を分析、プロセスを改善します。こうしたPDCAサイクルを回すことで、採用戦略を継続的に課題解決に結び付けていくことが可能になります。
採用活動を成功させるポイント
採用活動は、ただ応募者を集めるだけでは成功とはいえません。求める人材に出会い、入社してもらい、その後も長く活躍してもらうまでが一連のプロセスです。ここでは、採用を効果的に進めるために企業が押さえておきたいポイントを紹介します!
自社の魅力発信と採用ブランディング
優秀な人材に選ばれるためには、応募前から自社の魅力や価値観を効果的に発信しておくことが重要です。例えば、公式サイトや採用ページで社員インタビューや働く環境を紹介し、SNSで社内イベントや取り組みを発信するなど、求職者が「この会社で働きたい」と思える情報提供を行いましょう。企業のビジョンや文化を一貫して打ち出す採用ブランディングによって、自社にマッチする人材を惹きつける効果が高まります。
丁寧なコミュニケーションと信頼関係構築
採用プロセスにおける候補者との向き合い方も重要です。応募から内定に至るまで、迅速かつ丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。応募受付の連絡、面接後のフィードバック、内定通知時のフォローなど、一つひとつの対応が候補者の信頼感に直結します。特に内定後から入社までの間に懇親会などを実施し、入社意欲を維持するとともに不安を解消することで、入社辞退や早期離職の防止にもつながります。採用は入社がゴールではなく、入社後に戦力化するまでが一連の活動と捉え、関係構築を継続する姿勢が成功の鍵です。
ミスマッチを防ぐ仕組み作り
採用後のミスマッチによる早期離職は企業・本人双方にとって不幸な結果です。これを防ぐには、採用段階から自社とのフィット感を重視した選考を行うことが重要です。具体的には、事前に明確化した採用基準に沿って面接質問を用意し、志向や価値観を見極めます。また希望する働き方やキャリアパスについて率直にすり合わせを行い、お互いの認識違いをなくしましょう。さらに職場見学や社員との座談会の機会を設け、入社後のイメージを持ってもらう工夫も有効です。採用段階の丁寧な見極めと情報共有によって、入社後のミスマッチを大幅に減らせるでしょう。
採用のお悩み、「ねこのて」がサポートします
「どんな人材を、どのように採用すればよいのか分からない」「採用活動に時間やリソースを割けない」「定着しない」といったお悩みは、あらゆる企業に共通する課題です。
株式会社ねこのてでは、そんな悩みを抱える企業様の採用活動を、より効率的かつ本質的なものへとサポートしています。採用計画の立案から実務の運用、応募者対応まで一貫して支援が可能です。貴社にとって最適な人材を見極め、着実な採用につなげるためにも、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、貴社の課題に合わせたご提案をいたします。
まとめ
「採用とは何か」という問いに対する答えは、単なる人材獲得ではなく「企業の未来を創るための戦略的手段」だと言えます。本記事では、採用の基本的な意味や目的、そして経営・組織課題に結び付けた採用戦略の立案方法を解説しました。ポイントは、自社のミッション・課題を起点に採用計画を立てること、そして採用プロセスを通じて自社の魅力を発信しつつミスマッチのない人材を迎え入れることです。この戦略的な視点で採用活動に取り組むことで、単なる人数合わせではない真の組織力強化を実現できるでしょう。