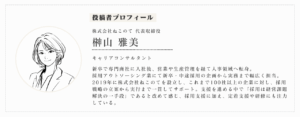求人票の正しい書き方 〜基礎編〜 基本ルール&NG表現を徹底解説
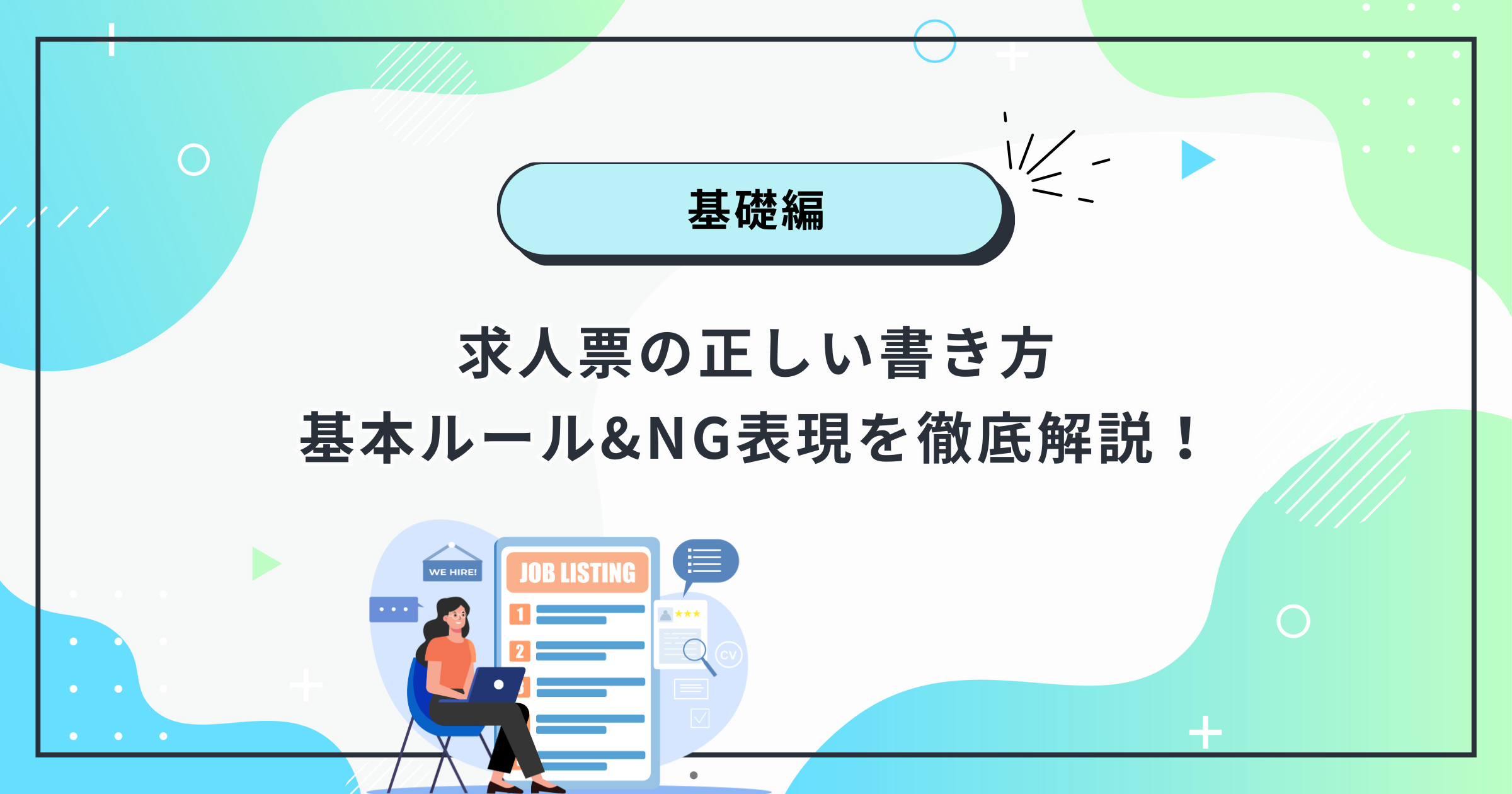
公開日:
求人票には必ず押さえるべき基本の書き方や、実は法律で禁止されているNG表現があるのをご存じでしょうか?
「応募が集まらない、思った人材からのエントリーが来ない」その背景には、求人票の基本を外してしまっているケースが少なくありません。せっかく募集を出しても、内容が不十分だったり、誤解を招く表現が含まれていたりすると、候補者は安心して応募できないのです。
本記事では基礎編として、求人票に必ず記載すべき基本項目を整理し、項目ごとの効果的な書き方のポイントや避けるべきNG表現について解説していきます!
求人票に必ず記載すべき基本項目
求人票には、法律で明示が義務付けられた基本的な労働条件が含まれます。求人票のフォーマットは掲載する媒体によっても異なりますが、以下の項目は漏れなく記載しましょう。
なお、職業安定法の改正は頻繁に行われるため、求人票の記載内容が最新の法令に準拠しているか定期的に確認しましょう。

参考:厚生労働省|令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
項目別にチェック!求人票の「伝わる」書き方
次に、これら項目を「伝わる」内容にするための書き方のコツを見ていきましょう。
求人票は、単に募集情報を羅列するのではなく、求職者に「ここで働きたい」と思ってもらえるような内容をしっかりと考えて書く必要があります。実際の求人票における各項目の書き方について、押さえておくべきポイントや表現の工夫を詳しく解説します!
タイトル(職種名)の書き方
求人票のタイトル(職種名)は、求職者が最初に目にする重要な箇所です。分かりやすく一目で仕事内容が想像できる表現にしましょう。「営業」「事務」など一語だけのタイトルや、社内でしか通用しない部署名・役職名は避け、一般的な職種名に言い換えることが大切です。例えば、「営業職募集」だけではなく「企画提案営業(ノルマ・新規開拓なし)」のように、具体的な職務内容や魅力的な条件を盛り込むと効果的です。タイトルに少し工夫を加えることで、求人検索結果で目立ち、求職者の興味を引くことができます。ただし、長くなりすぎるのも禁物です。端的かつ魅力的なタイトルで、まずは「この求人内容を詳しく見てみよう」と思わせましょう。
仕事内容の書き方
仕事内容の説明は、求人票の中核となる部分です。どのような業務を担当し、どんな役割を果たすのか、具体的に書くことが大切です。箇条書きで主な業務項目を整理し、誰が見てもイメージしやすいようにするといいでしょう。「営業活動」など一言で済ませず、「問い合わせ対応から契約締結まで一貫して担当いただきます」のように、実際の業務フローや範囲を明示します。
また、専門用語や社内独自の言い回しは避け、誰にでもわかるように噛み砕いて説明することも忘れてはいけません。応募者はその業界や職種に不慣れな場合も多いため、平易な言葉に置き換えることで仕事内容が伝わりやすくなり応募へのハードルも下がります。
さらに、職場の雰囲気やチーム構成、1日の仕事の流れなども補足として加えると、求職者が働く姿を具体的にイメージしやすくなります。特に未経験者を想定する場合には、業務内容だけでなく「どんなサポート体制があるか」まで伝えると、より安心感を与えることができます。
応募資格・求める人物像の書き方
応募資格や求める人物像の欄では、必要な経験・スキル要件を明確かつ適切なボリュームで示すことがポイントです。必須条件が多すぎると応募を敬遠されてしまい、逆に少なすぎるとミスマッチを招きます。そのため、「最低限これは欠かせない」という必須条件と、「あると望ましい」という歓迎条件を分けて記載
すると良いでしょう。
例えば、
【必須条件】
・普通自動車運転免許
・営業経験3年以上(業界不問、法人/個人営業不問)
【歓迎条件】※あれば尚
・IT業界での営業経験
・マネジメント経験
このように区別することで、応募者は自分が条件を満たしているか判断しやすくなりますし、自信のない方でも「歓迎条件なら無くても応募してみよう」と思えるようになります。
また、求める人物像も具体的に書きましょう。「コミュニケーション能力が高い方」など抽象的な表現だけではなく、「社内外の関係者と円滑に調整ができる方」のように、その仕事で求められる資質を具体的に示すと伝わりやすくなります。なお、後述する通り年齢や性別等での制限は法律で禁止されていますので、「35歳まで」「女性限定」等の表現はNGです。代わりに、「第二新卒歓迎」「〇〇の実務経験〇年以上」など、能力や経験に基づく表現でターゲットを伝える工夫をしましょう。こうした記載により、企業が求める人物像が明確になり、双方にとってミスマッチの少ない応募につながります。
勤務条件・待遇の書き方
勤務条件や待遇に関する情報は、求職者が特に気にするポイントです。勤務時間や休日体系、残業の有無、給与水準などは詳しく正直に記載しましょう。例えば、「勤務時間: 9:00~18:00(平均残業月20時間程度)」や「休日: 完全週休二日制(土日)・祝日、年間休日120日」など、数字を用いて具体的に示します。残業時間については、「残業なし」と謳って実際は発生するような場合はトラブルの元ですので、繁忙期はどの程度発生するのかなども含めて正直に書くことが大切です。
給与についても同様に、「月給◯万円~◯万円+賞与年2回」といった形で明示します。賞与や昇給、各種手当(例:住宅手当・資格手当など)がある場合はその旨を記載し、将来的な昇給モデルや年収例を示すのも効果的です。例えば「初年度年収例:◯万円」「入社3年目主任職・年収◯万円」などと書くと、入社後のイメージがしやすくなります。
また、試用期間があればその長さと待遇の差異、リモートワークやフレックスタイム制度の有無、有給休暇取得率や産休育休の取得実績など、福利厚生面でアピールできることは積極的に盛り込みましょう。こうした勤務条件の情報は法的にも明示が義務付けられていますが、単に義務だから載せるのではなく、自社の魅力を伝える材料と捉えて丁寧に書くことがポイントです。
求人票作成で避けるべきNG表現
最後に、求人票で避けるべき表現や注意すべきポイントを確認しましょう。求人票作成においては、まず法律に従い、差別のない正確な表現にすることが優先されます。それぞれ具体例を挙げて解説します。
※年齢を制限・差別するような内容
※人種・国籍・出身地・身体的特徴・障害等を差別する内容
※虚偽・誤解を招く内容(誇大表示を含む)
性別を制限・差別するような内容
募集・採用で性別による差別は法律で禁止。文言・選考運用の双方で均等な取扱いが必要です。
OK例:「顧客対応(重量物の扱いなし)」「5kg程度の機材搬送あり」※業務実態を中立表現で明示
▼チェック
性別で条件や説明を変えていないか/職務要件は業務に必要な範囲か(身長・体重などを不用意に要件化していないか)
年齢を制限・差別するような内容
募集・採用での年齢制限は禁止。例外事由は限定され、根拠のない上限・下限設定や運用は違法です。求人票は「年齢不問」とし、実務でも年齢を基準に扱わないこととされています。最新の例外事由は厚労省資料で確認ください。
OK例:「長期的なキャリア形成を図るため、〇〇歳まで」「第二新卒歓迎」※能力・経験に基づく表現へ
▼チェック
タイトルや本文、社内運用で年齢を選別していないか/例外を使う場合は該当根拠を明示できるか
人種・国籍・出身地・身体的特徴・障害等を差別する内容
差別や人権侵害につながる表現は不可です。障害者であることを理由とする差別は禁止で、選考では合理的配慮の提供義務があります。国籍・人種・民族等に触れる表現は避け、中立記述を徹底する必要があります。
OK例:「在留資格に基づき就労可能な方」「日本語での業務コミュニケーション(目安:〇〇レベル)」
▼チェック
出身・国籍・身体的特徴に触れていないか/業務遂行に不要な条件を付していないか/合理的配慮の想定・案内があるか
虚偽・誤解を招く内容(誇大表示を含む)
求人情報は虚偽・誤解表示の禁止および的確な表示義務があります。条件は正確・最新に更新し、誇張語は根拠と併記する必要があります。
OK例:「完全週休二日(土日・祝)・年間休日120日」「平均残業 月20h(直近12か月実績)」/優位表現は出典明記
▼チェック
就業場所・賃金・勤務時間などの重要条件に齟齬がないか/更新時期・根拠資料の管理体制があるか
このように、法律に触れる表現・誤解を招く表現・求職者目線に立っていない表現はNGです。自社の求人票にそうした記載がないか、必ずチェックしましょう。
まずは求人票の基礎を整えるところから、専門家に相談しませんか?
今回ご紹介した「基礎編」の内容を踏まえて自社の求人票を見直すと、改善の余地が見えてくるはずです。
株式会社ねこのてでは、求人票の基礎的な整備から、採用ターゲットに合わせた応用的な設計まで、専門スタッフが一貫してサポートしています。自社だけでは気づきにくいポイントも客観的に確認できるため、応募数の増加やミスマッチの防止につながります。「自社の求人票に改善の余地があるか知りたい」「応募が集まらない原因を知りたい」と感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
※「記事を読んで問い合わせ」と一言添えていただけるとスムーズです。
まとめ
本記事では「基礎編」として、求人票に必ず記載すべき項目や、各項目の効果的な書き方、そして避けるべきNG表現について整理しました。これらの基本をしっかり押さえることで、応募者に安心感と信頼感を与え、ミスマッチを防ぐための土台を築くことができます。
ただし、求人票は「書けば終わり」ではありません。同じポジションでも、ターゲット層によって響く表現や強調すべきポイントは変わります。より効果的に応募を集めるためには、ターゲットに合わせたカスタマイズや表現の工夫が欠かせません。
次回の【応用編】では、採用ターゲットに合わせた求人票のカスタマイズ方法や、さらに応募を集めるための実践的な工夫について詳しく紹介します。ぜひお楽しみにしてください。