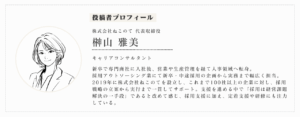求人票の書き方のコツとは? 〜応用編〜 応募を増やすターゲット別実践法
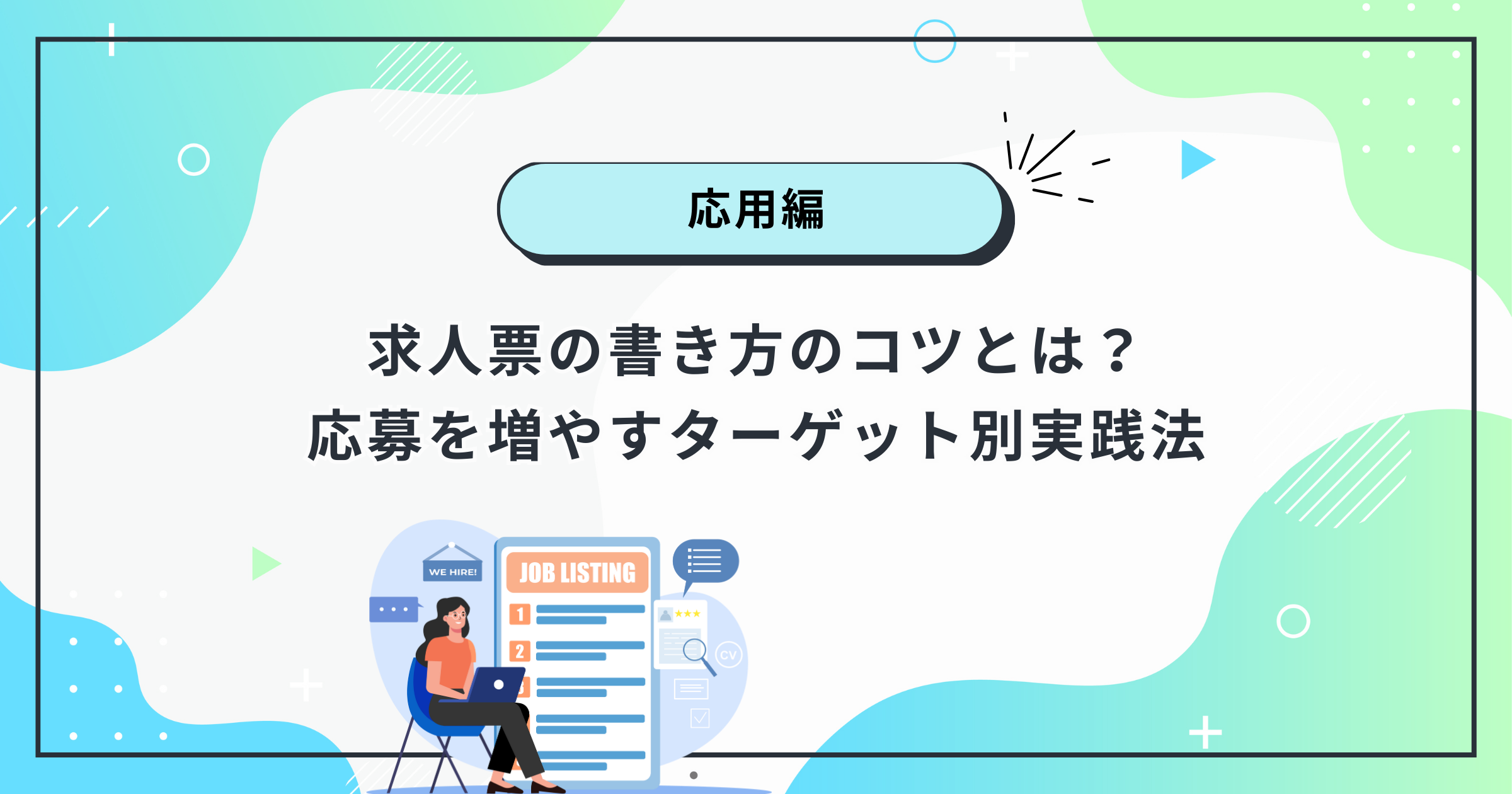
公開日:
「求める人材からの応募がなかなか来ない…」と感じるなら、求人票の伝え方を見直すタイミングかもしれません。前回のコラムでは『求人票の正しい書き方 〜基礎編〜 基本ルール&NG表現を徹底解説』として、必須項目や注意点を整理しました。今回はその【応用編】です。一つのポジションであっても、候補者の背景や志向性に合わせて複数の求人票を用意することで、応募の成果は大きく変わります。本記事では、採用現場で実際に成果を上げている“ターゲット別書き分け”のノウハウを、具体例とともに紹介します!
なぜ一律の求人票では成果が出ないのか?
求人票は採用活動の入り口ですが、すべての候補者に同じ内容を提示しても十分な成果は得られません。ここでは、一律の求人票がなぜ成果につながりにくいのか、その背景と具体的な理由を解説します。
言葉遣いの調整だけでは応募者に刺さらない
求人票をターゲット別に書き分けようと考えたとき、表面的には「若手向けにはカジュアルな言葉遣いで」「ベテラン向けには丁寧なトーンで」といった表現の調整を思い浮かべるかもしれません。しかし、言葉遣いを工夫するだけでは不十分です。大事なのは、その一歩先にある「提供する価値」をターゲットごとに変える視点です。つまり、単に文章を言い換えるだけでなく、各ターゲット層が転職を通じて得たい価値(キャリアの展望や成長機会など)にフォーカスした求人票にしなければ、本当に響く内容にはなりません。
ターゲットごとに求める「価値」が異なり、画一的な内容では響かない
求職者が転職で求めるものは異なります。給与や福利厚生は当然気にしますが、それ以上に「この会社で何ができるのか?」「自分のキャリアはどう成長するのか?」といった「自分にとってのメリット」を探しています。ある求職者は新規事業への挑戦を求め、別の求職者はワークライフバランスの向上を重視する、といった具合に価値観はさまざまです。そのため、画一的な求人票では特定の層の心に響かず、「誰に向けても当てはまるが誰の心にも刺さらない」内容になりがちです。求める人材像ごとに提供できる価値を見極め、それを反映した求人票にすることが成果を出す第一歩となります。
ターゲット別に求人票を書き分けるメリット
次に重要なのが「誰に向けてどのように訴求するか」です。ターゲット別に求人票を分けることで、応募数やマッチ度が大きく変わります。ここでは、求人票を書き分けることで得られる主なメリットを解説します!
求人票の訴求力向上による応募数アップ
ターゲットに合わせて求人票の内容を調整すると、訴求力が飛躍的に向上し、限られたリソースでも「刺さる求人票」を作れるようになります。その結果、本当に欲しい人材からの応募を増やすことが可能になるのです。例えば自社の魅力をターゲットに合わせて伝え直した結果、今まで応募が来なかったポジションに複数の応募が集まるようになった、といったケースも珍しくありません。訴求力の高い求人票は、会社の知名度に関わらず求職者の目に留まりやすく、結果として応募母集団の拡大につながります。
求める人材からの応募獲得率・マッチ度の向上
ターゲット別に求人票を書くことで、未経験者向けにはスキルアップの魅力を、経験者向けには裁量や年収アップといったメリットを強調するといった具合に、伝えるポイントを明確化できます。その結果、各ターゲットが「自分向けの募集だ」と感じやすくなり、本当に欲しい層からの応募数が増えるのです。実際、一つの求人に未経験者向けと経験者向けの情報を詰め込むと、未経験者には「自分には無理そう」、経験者には「この内容でこの年収は合わない」と判断され、誰にも響かない中途半端な内容になりがちです。求人票をターゲット別に作成することで、応募前に『自分には合わないかも』と候補者が判断してしまうのを防げるため応募者の質・マッチ度も高まります。
実践ステップ!効果的な求人票書き分けの進め方
求人票を複数に分ける際、思いつきで文章を変えるだけでは成果につながりません。大切なのは、理想の人物像を明確にし、そのターゲットに合わせて訴求ポイントを整理することです。ここからは、求人票を書き分ける際に欠かせない基本ステップを解説します。
採用ターゲットの明確化:応募してほしい人物像を具体的に設定
まず取り組むべきは、採用ターゲットの明確化です。いくら応募者数が増えても、採用したいスキル・経験を持った人でなければ本末転倒だからです。そこで、自社が本当に来てほしい人物像をスキル、経験、志向性、価値観レベルまで具体的に描きましょう。例えば「事業会社のマーケティング職として5年、商品企画から販促まで幅広く携わってきた30代前半。自社商材だけでは経験の幅が限定される点に課題を感じ、より多様な業界でスキルを活かせる環境を求めている人材」など、できる限り具体的に定義します。その際、自社内で活躍している社員の共通点を洗い出したり、現場の声を拾ったりすることも有効です。さらに、そのターゲット人材が現職で感じている悩みや、転職で実現したいことをリストアップしてみてください。ターゲット像を具体化し、悩み・願望を把握することで、次のステップで提供すべき価値が見えてきます。
▼採用ターゲットの詳しい設定方法は以下で解説しています!
関連記事:採用ターゲットの設定方法とペルソナ活用術|ポイントは「組織の課題解決」目線!
コア情報は共通化しつつ、ターゲット別に訴求メッセージを調整
採用ターゲットが定まったら、求人票のコア情報と訴求メッセージを切り分けて考えます。募集ポジション自体の基本情報(仕事内容や応募条件、勤務地など)は全ての原稿で共通にしつつ、訴求点や強調するポイントはターゲットごとに変えるアプローチです。このとき注意したいのは、複数の原稿間で矛盾や不整合がないようにすることです。こうすることで、どの原稿を読んだ候補者にも事実関係は正確に伝わりつつ、より多くの「応募したい人材」にリーチが可能になります。
次章からは実際に、ターゲットの在籍企業・価値観・キャリア層ごとに、どのように求人票を変えるべきか具体的なポイントを解説します。
書き分けポイント①ターゲットの在籍企業に合わせた訴求
前述で当社の事例でもご紹介しましたが、候補者がどのような企業に在籍しているかによって、響くメッセージは大きく変わります。
大企業出身者向け:裁量権の大きさや幅広い業務経験を強調
大企業在籍者には、現在感じている物足りなさを解消できる環境であることを訴求するといいでしょう。大企業では安定した環境で部分的な業務に従事しているケースが多く、「裁量の少なさ」や「意思決定の遅さ」に不満を抱きがちです。そこで求人票では、「自由度が高くフラットな組織で自分のアイデアをダイレクトに製品に反映できる」「少人数のチームでスピード感を持って開発を進められる」といったメッセージを前面に出します。大企業出身者が今まさに感じている制約(例:決裁に時間がかかる、業務範囲が限定されている等)が解消され、より大きな裁量を持てることを具体的に示すことで、「今の課題をここなら解消できそうだ」と感じてもらいやすくなります。
中小・ベンチャー出身者向け :安定性・充実した福利厚生をアピール
中小企業やスタートアップ在籍者には、これまでになかった安定基盤やサポート体制をアピールします。ベンチャーで働いた経験がある人は、自由度やスピード感には慣れている一方で「資金基盤の不安定さ」や「プロジェクトが突然頓挫するリスク」を痛感している場合があります。求人票では、「安定した資金基盤のもとで伸び盛りのサービス拡大に携われる環境」や「これまで培ったスピード感やチャレンジ精神を活かしつつ、中長期的なキャリアを築ける職場」といったメッセージを打ち出すことで、「自分の強みを発揮しながらも腰を据えて働けそうだ」と共感を得られやすくなります。さらに福利厚生や研修制度など、手厚いサポート体制にも触れることで、安定志向の人材にも訴求力の高い求人票となるでしょう。
書き分けポイント②ターゲットの属性・価値観に合わせた訴求
同じ職種でも、求職者が転職に求める価値は「キャリアアップ」から「安定志向」まで千差万別です。個人の志向性や価値観を理解し、それに沿ったメッセージを届けることが応募意欲を高める鍵になります。
ターゲットごとに転職で求めるものはさまざま
求職者は、「年収アップ」や「新しい技術への挑戦」「社会貢献の実感」を重視する人もいれば、一方で「より良いワークライフバランスで働ける環境」「安定した企業で腰を落ち着けたい」と考える人もいます。こうした多様なニーズに応えるには、求人票においてターゲットごとに刺さる情報を提供することが欠かせません。単に業務内容を説明するだけでなく、「この会社で何が得られるのか」という未来像を描き、ターゲットが自分自身の希望と重ね合わせられる情報を盛り込むことが、応募意欲を高める鍵となります。
アピール内容をどう変えるか:向上心旺盛な人 vs チーム志向の人
ターゲットの志向性によっても、響くメッセージは変わります。自己成長意欲が高い人に応募してほしい場合、求人票では「どのような成果を上げれば正当に評価されるか」「自己研鑽をどう支援しているか」といった情報をしっかり伝える必要があります。具体的には、成果主義の評価制度やスキルアップの機会(例:社内勉強会や資格取得支援)があれば強調するといいでしょう。一方、チームワークを重んじる人を求めるなら、「現在のチーム構成や各メンバーの役割」「周囲と連携して業務を進める体制」といった情報をアピールしましょう。「少人数チームで密にコミュニケーションを取りながら働ける環境」「部署横断のプロジェクトで協力し合える文化」といった記載が考えられます。向上心旺盛な人には挑戦と成長のビジョンを、チーム志向の人には協調と安心感のビジョンを示すことで、それぞれのタイプに「この職場なら自分の志向に合っていそうだ」と感じてもらいやすくなります。
アピール内容をどう変えるか:ワークライフバランス重視 vs キャリア重視
安定志向が強くワークライフバランスを重視する人もいれば、成長志向が強くキャリアアップを最優先する人もいます。安定志向の人には、休日休暇の充実や残業の少なさ、福利厚生など安心して働ける要素を詳しく伝えると効果的です。一方、成長志向の人には、新規事業への挑戦機会や研修制度、将来的なキャリアパス展望などキャリア面の魅力を強調しましょう。例えば、前者には「有給取得率◯%」「リモートワーク制度あり」といった情報、後者には「将来○○事業の立ち上げに携われる」「入社◯年で管理職登用の実績あり」といった情報が響きやすく、それぞれの志向にマッチした訴求が可能になります。
書き分けポイント③キャリア層(若手~中堅)に合わせて調整
キャリア層ごとに重視するポイントは異なりますが、年齢だけで単純に区分できるものではありません。実際には「職種(バックグラウンド)×年齢」の掛け合わせで捉える必要があり、同じ年代でも職種やキャリアパスによって響く要素は変わります。ここではあくまで年代ごとの一般的な傾向を解説します。
若手・20代向け:成長機会や手厚い研修サポートを強調
20代の若手層に向けては、成長意欲を満たし不安を解消する情報を重視しましょう。20代は社会人経験が浅く、失敗への不安を抱えつつも自身のキャリアの方向性を模索している時期です。この年代はスキル習得や経験の幅を広げるチャンスを求めており、積極的に挑戦できる環境を好む傾向があります。そのため求人票では、「未経験でも挑戦できる充実した研修制度」「早期に大きな仕事を任せてもらえる社風」といったメッセージを打ち出すと効果的でしょう。また、ワークライフバランスや福利厚生の充実度にも敏感な世代のため、「フレックスタイム制で柔軟な働き方が可能」「年間休日◯日でプライベートも充実」といった記載も安心感につながり、応募を後押しします。
中堅・30~40代向け:キャリアアップ要素や大きな裁量権を訴求
30~40代の中堅層には、これまでの経験を踏まえて更なるキャリアアップが望める点を訴求します。この層は豊富な実務経験に加え、マネジメント経験を持つ人も増えてきます。また、家庭や生活の安定も重視するため、転職に際しては慎重になりやすい年代です。求人票では「マネージャー候補としてチームを牽引できる」「実績次第で事業責任者への道も開けるポジション」など、意思決定に関与できる裁量権やキャリアの先を見据えた役割を提示すると興味を引きやすいでしょう。同時に、報酬や待遇の充実、柔軟な働き方(リモートワーク可否やフレックス制度)などについても触れ、家庭と仕事を両立しやすい環境であることもアピールしましょう。「経験を活かして飛躍できる舞台」と「安心して長く働ける条件」の両方を伝えることで、応募意欲を高めることができます。
ターゲット別に「伝わる求人票」を、プロと一緒に設計しませんか?
本記事でご紹介したように、同じポジションでも候補者の在籍企業・キャリア層・志向性に合わせて求人票を分けることで、応募数やマッチ度は大きく変わります。とはいえ、実際に自社で複数の求人票を用意し、適切に運用・改善を重ねるのは時間も労力もかかるものです。
株式会社ねこのてでは、採用ターゲットの明確化から求人票の複数パターン設計、効果測定と改善までを一貫してサポートしています。現在運用中の求人票や応募状況を共有いただければ、「どこをどう書き換えれば成果につながるか」を具体的にご提案可能です。
採用成果を高めたいとお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※「記事を読んで問い合わせ」と一言添えていただけるとスムーズです。
まとめ
これまで見てきたように、一律の求人票では候補者の心に響かず、応募に結びつきにくいのが現実です。ターゲットごとに訴求点を変え、在籍企業や志向性に寄り添った情報を届けることで「自分のための求人だ」と感じてもらいやすくなります。実践ステップで紹介したように、まず採用ペルソナを明確にし、訴求メッセージを調整しながら継続的に改善を行いましょう。基礎編で学んだ「必須項目とNG表現」に加えて、本記事の応用編を取り入れることで、応募数やマッチ度を高める実践的な採用活動が実現できます。